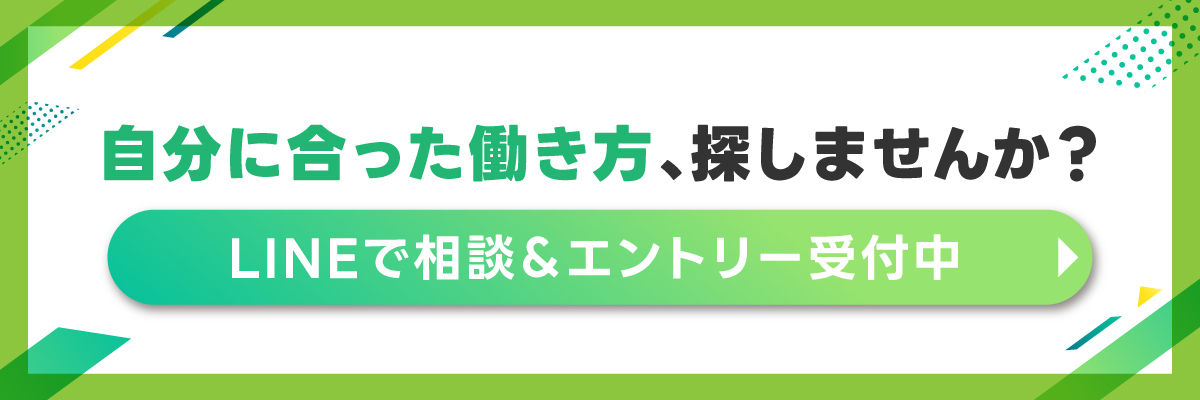「改善しているのに、なぜか成果につながらない。」…仕事でそんな経験、ありませんか?
多くの人が「ミスを減らす」・「効率を上げる」といった「業務改善」に取り組んでいます。しかし、改善をしても、成果が出る人とそうでない人がいます。
その違いを生むのは「何のために改善するのか」を考えられるかどうかです。
だからこそ、ミショナは「目的を意識して、課題を改善する力」を採用で重要視しています。私たちはこの力を「目的志向の改善力」と呼んでいます。
【例で見る】「目的志向の改善力」とは何か?

「目的志向の改善力」とは、「目的を意識して、課題を改善する力」のことを指します。
この力は、より質の高い成果を生み出すために必要不可欠です。以下で例を用いて、わかりやすく解説します。
「目的志向の改善力」を発揮できているケース
たとえば、「作成したレポートがわかりにくい」という課題があったとします。
目的志向の改善力を発揮できる人は、次のステップで考えます。
- まず、“何のために”レポートを直すのか、目的を明確にする(目的設定)
例:「見る人が迷わず、短時間で内容を理解できるようにする」 - 次に、その目的を妨げている原因を洗い出す(課題の整理)
例:「全体的に文字数が多くて理解しづらい」 - 目的を達成するための改善策を考える(改善策の設計)
例:「文字を減らす」・「グラフを使う」 - 改善策を実行し、“目的が達成できたか”を確認する
例:「第三者に読んでもらい、すぐ理解できるかを確認する」
このように、目的から逆算することで、「文字を減らす」・「グラフにする」など、成果につながる改善だけを実施できます。
「目的志向の改善力」を発揮できていないケース
反対に、次のような行動をしてしまう場合は、この力が発揮されているとは言えません。
- そもそも、“何のために直すのか”を考えずに修正を始めてしまう
例1:「とりあえず色やレイアウトを変えてみる」
例2:「とりあえず文章を短くしてみる」 - 目的がずれたまま作業をしてしまう
例1:「おしゃれに見せるためにデザインを変える」
例2:「手間を減らしたいから情報を削る」
このような行動をしてしまうと、改善に取り組んだとしても成果につながらず、せっかくの作業が無駄になってしまいます。
ミショナが「目的志向の改善力」を持つ人材を求める理由

ミショナは、日々の業務の中で課題を見つけ出し、改善を積み重ねることで、より質の高い成果を生み出していきたいと考えています。
このような考えは、弊社の企業理念の1つである「常に改善を重ねる姿勢」として現れています。そして、この理念を実現するうえで不可欠なのが「目的志向の改善力」です。
この力が欠けていると、見当違いの改善に時間を使ってしまい、より質の高い成果を生み出すことはできません。そして、「常に改善を重ねる姿勢」の実現も難しくなってしまいます。
だからこそ、弊社は「目的志向の改善力」を持つ人材を求めているのです。
現場でどう活かされる?「目的志向の改善力」の事例紹介

ここでは、「目的志向の改善力」がミショナの業務でどのように発揮されるかを、実務を想定した事例としてご紹介します。
なお、より具体的にイメージしていただけるよう、スタッフの視点で事例を構成しています。
応募者様の声を元にプロセスを再設計
採用対応を行う中で、応募者様から同じ質問が繰り返されていることに気がつきました。
最初は単に「問い合わせ数を減らしたい」と思っていましたが、改めて目的を見つめなおすと、設定すべきゴールは「応募者様が不安なく、スムーズに選考を進められること」であると感じました。
そこで、どんな情報が求められているのかを改めて分析し、FAQ(よくある質問)に記載。
FAQのカテゴリの再構成も行い、より直感的に情報を探せる構成へと改善しました。
改善後は、問い合わせ件数が減少しただけでなく、応募者様が自ら疑問を解消できるようになり、次の選考ステップへの移行率も向上しました。
「応募者体験をより良くする」という目的を軸に改善を重ねた結果、組織にも応募者様にも良い変化を生み出すことができたと感じています。
こちらは業務効率化だけを目的とした改善ではなく、応募者様の利便性を重視したプロセス設計を行っている事例です。
目的を「応募者体験の向上」に置いた結果、業務プロセス全体の効率も向上することにつながっています。
目的を見据え、データを基に体験価値を磨き続ける
サービスに新しい機能を追加した際、ユーザーの操作データを分析すると、利用途中での離脱が目立ちました。
「もっと使いやすくしよう」という発想だけで終わらせず、「なぜユーザーが離脱してしまうのか」・「この機能で届けたい本当の価値は何か」を改めて考えました。
チームで目的を再確認し、「ユーザーが迷わず価値にたどり着ける体験を作ること」をゴールに設定。データを基に仮説を立て、導線や文言など細かな部分を継続的に見直しました。
その結果、離脱率は徐々に低下し、最終的に大幅に改善しました。
こちらは、目的を起点にした継続的な改善活動が成果を生んだ事例です。
「改善そのもの」を目的にするのではなく、ゴールから逆算して改善を重ねる姿勢こそ、ミショナが大切にしている「目的志向の改善力」を体現しています。
まとめ

「目的志向の改善力」は単に効率を上げる力ではなく、「目的を意識して、課題を改善する力」です。
ミショナがこの力を大切にしているのは、私たちの理念である「常に改善を重ねる姿勢」を、日々の行動として実践するために欠かせない基盤だと考えているからです。
とはいえ、目的志向の改善力が最初から身についている必要はありません。「もっと良い成果を出したい」という前向きな姿勢があれば、この力は着実に伸ばしていけます。
だからこそミショナは、そうした姿勢を持ち、目的を意識しながらより良い仕組みづくりに向き合える方と、一緒に働きたいと考えています。